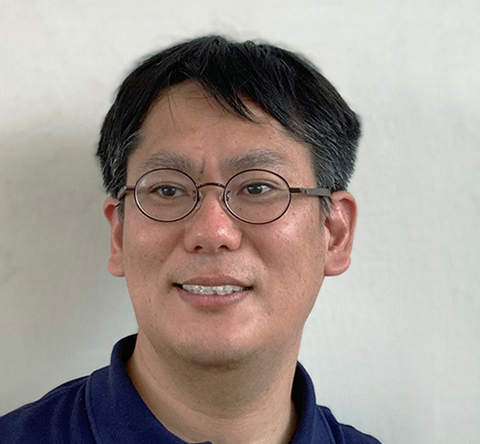- 掲載:2024年05月07日 更新:2024年05月07日
お施主様と共に創り上げた「床に座す家」
設計:トミオカアーキテクトオフィス 冨岡 繁

一年検査の時に奥様から「私、幸せです」という言葉を頂きました。これが一番の報酬でした。畑は大きすぎて、まだ全体を活用できていませんが、その整備もひつとの楽しみになっているなと感じました。
設計士プロフィール
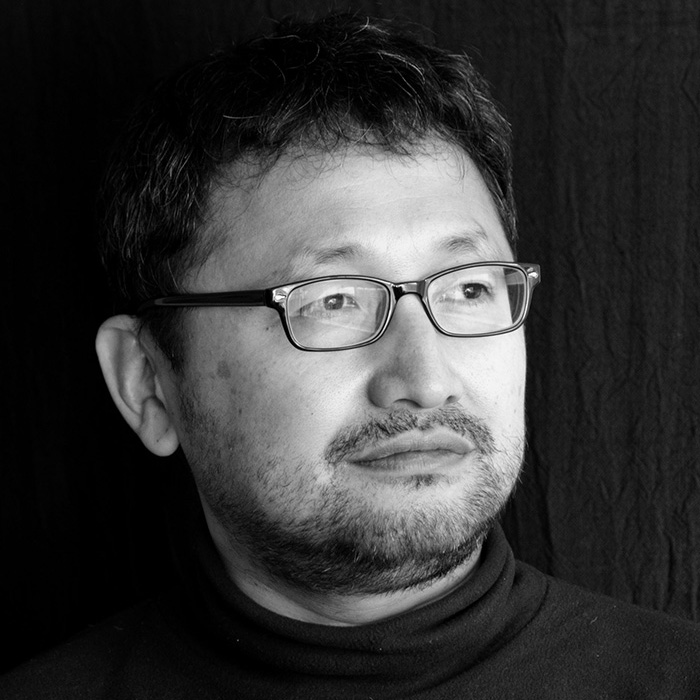
TOMIOKA SHIGERU
福岡県福岡市南区高宮3-10-1
ヒルサイド高宮402
~1993年 清水建設設計本部
~1994年 世界放浪の旅(笑)
~1999年 マルタ設計(東京)
1999年 東京から福岡に移住
~2004年 志賀設計(福岡)
2004年~ トミオカアーキテクトオフィス
2021年~ 愛知産業大学非常勤講師
好物:とんこつラーメン・いも焼酎・小石原焼・山
好きなアーティスト:クリムト・ミュシャ・佐伯祐三
市街化調整区域の土地を敷地に活用

敷地購入を含めて超ローコストで作る必要がありましたので、敷地選定の段階から候補地見学に同行させて頂きました。最終的に敷地は安価に入手できる市街化調整区域で、開発という法的な手続きを経て住宅建設を可能としました。市街化調整区域の安価な土地を敷地とすることで、かなりゆったりとした計画が可能になりました。予算上建物は大きくは作れませんが、4~5台停められる駐車場と南側には畑スペースも確保できました。
ローコストであっても拘るところは拘りました。予算の中で何ができて何ができないのかを一緒に取捨選択しました。
折角大き目の敷地なので、将来老後のことも見越して基本的には平屋建てで計画しました。但し花火が良く見えるように一部ロフトスペースを設けて大きな窓を開けています(法的には二階建てにしています)。
建物全体で断熱性能を上げる

構造的には外壁部分を全て耐力壁として構造用合板を貼り、接合部にはテーピングして建物の気密性を上げます。更には外断熱として二重に気密をとり建物全体で温度フローを考えました。これは屋根も同じで合板と断熱材の接合部には全て気密テープを貼っています。ワンルーム状の大きな空間なので、個別の室ではなく建物全体で断熱性能を上げるという考え方です。
また、基礎断熱として床下も室内と同一の温度領域と考え、床下とロフトの天井付近をダクトで繋いで、気流方向の逆転が可能な換気扇(カウンターアローファン)を設けました。夏場は外気温よりも低い床下の空気を上部へダクティングし、逆に冬場は上部に滞留する温度が高い空気を床下へと循環させています。同時に室内はシーリングファンで空気をかき混ぜます。
また、基礎断熱は基礎外部に断熱層を設けることで、そのコンクリート部分は底盤と合わせて蓄熱材として利用しています。
子供部屋はLDKと一体の空間に

建物はよくある個室をたくさん分けるようなプランではなく、家族全体でワンルームに住むようなものをご希望でした。但し、来客時などには個室化できる空間、将来的には個室化できる子供スペース、防音も考えた主寝室等は設けることにしました。
またLDKからはお子様が学校から帰って来る様子がキッチンから見えるようにとのご要望も頂きました。キッチンだけでなくワンルーム状の家全体、どこからでも通学路は見えます。街の中心部であれば逆に外からの視線が気になりますが、郊外であるからこそ可能となりました。
但しある程度はプライバシーを確保できるように、ブラインドは上部と下部で別々に視線をカットできる、タチカワのパーフェクトシルキースリーウェイを取り付けました。更には前面道路越しに地元の花火大会を見る場所も欲しいと言われました。
外壁に地震力を負担させることで内部に設ける壁の量を減らす

外壁に地震力を負担させることで内部に設ける壁の量を減らし、コストを削減すると共に将来のリフォームにも対応できるよう考えました。主寝室のみ遮音を考えて壁兼用の本棚で囲みましたが、これも将来的には撤去又は移設が可能です。
お子さんがまだ小さいことから、子供部屋はLDKと一体の空間としましたが、これは後で仕切れるように間仕切り兼用の家具を最初から安価に大工工事で作ってもらいました。最初は部屋の隅に置いて収納に使います。合わせて将来設置する建具用の吊りレールは最初から埋め込んであります。子供たちはある程度の年齢になったところで個室として利用できますが、独立して家を出た場合そのスペースはLDKの一部に戻ります。
建物内動線も家族と来客とが玄関から先は別方向でとれるようにしています。来客は建具で閉じることもできる客間に直接玄関から入れます。トイレも玄関に付随する形なので利用可能です。一方家族は土間収納経由で洗面と浴室、キッチン裏にアクセスできます。お子さんが汚れて帰ってきたときは洗面で手を洗い、時には直接浴室に行く事もできます。家族の靴は玄関内で雑多になりがちですが、土間収納内部であれば閉じてしまえば来客に見られることもありません。水まわりでなくキッチンの方に出ればそこはもうワンルーム状のメイン空間です。
こだわりをもった建材を使用
サッシも樹脂とアルミ複合の断熱サッシにして(TOSTEMサーモスシリーズ)、ガラスもペアガラスです。やや価格的には高い印象のTOYOキッチンのアイランド型キッチンも、今はありませんが当時廉価モデルであったポルトシリーズを入れました。レンジフードは他メーカーの物をキッチン工事とは別につけてコストを節約しています。 床材はサンワカンパニーのアカシア無垢フローリングです。内壁は石膏ボードにSK化研のエコフレッシュクリーンという水拭きのできる合成樹脂エマルションペイントを塗っています。基礎断熱で地面から1mまでは防蟻処理されたスタイロフォームAT、上部壁と屋根も外断熱でスタイロフォームを使っています。床下と室内天井上部はダクトで繋いで、ダクト内蔵型の三菱カウンタアローファンを取り付けています。
また室内の空気を循環させるためにコイズミのシーリングファンも天井に付けています。
フローリングは無垢材ですが、杉材ではなく当時安価であったアカシアを採用しています。これは施主が見つけてきたものです。壁の塗料は防カビ性や抗菌性をもっていますが、何より通常のエマルションペイントと違うのは水拭きができるところです。またビニールクロスと違って塗装は施主が自分で塗り重ねもできます。床材の塗料もオイル系の物を使う事で、木材の呼吸を妨げることなく、また施主が自分で塗り重ねていく事ができます。竣工後訪れる度に塗り重ねられていて、どんどんと艶やかにその表情は変わっていってます。
家具もダイニングテーブルは本工事です。テーブルと言っても掘りごたつ式になっていて、天板は二重で間に布団を挟んで、冬場は本当に炬燵になります。炬燵布団は施主の手作りです。床に空いた窪み部分にはコンセントが用意してありますので、炬燵用の電気ヒーターを置くことができます。天板は贅沢にウォールナット材を使いました。突板ではなく集成材です。しかも短手方向には継ぎ目の無い幅はぎ材です。ソファーもありません。
テレビの前に掘り込みリビング

テレビの前に掘り込み部分を作って、その縁に座れます。
下部は収納スペースになっているので、テレビまわりのごちゃごちゃとするものもすっきりここに納まります。基礎断熱で床下が部屋内と同じ温熱環境になっているので実現できています。
「冨岡 繁」氏の他の作品
設計士プロフィール
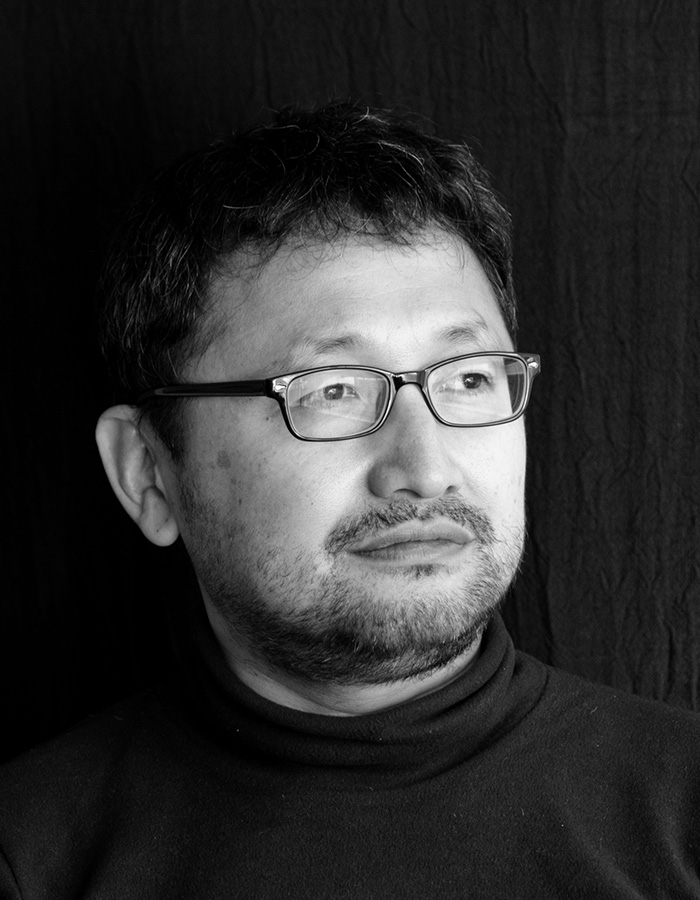
TOMIOKA SHIGERU
福岡県福岡市南区高宮3-10-1
ヒルサイド高宮402
~1993年 清水建設設計本部
~1994年 世界放浪の旅(笑)
~1999年 マルタ設計(東京)
1999年 東京から福岡に移住
~2004年 志賀設計(福岡)
2004年~ トミオカアーキテクトオフィス
2021年~ 愛知産業大学非常勤講師
好物:とんこつラーメン・いも焼酎・小石原焼・山
好きなアーティスト:クリムト・ミュシャ・佐伯祐三